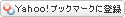令和元年10月6日、中日新聞
続「共同親権の展望」(上)解けない対立 早川昌幸(読者センター)
「報道していただき、心から感謝しています。苦しんでいる人たちの実情を社会が認識し、支える土壌が出来上がっていくのではないか、と期待しています」
「私も当事者で、いろいろな被害者と会い、苦しみを耐え抜いてきました。仲間たちも、この記事を見て涙しております」
前回の特集(本欄七月七、十四日付)に、男女の当事者らからさまざまな意見が寄せられた。
◆世界の潮流に遅れ
離婚後共同親権を認めていないのは、先進七カ国(G7)では日本だけであり、国連の子どもの権利委員会が今年、日本に「児童の共同親権を認めるため」の法改正を求める勧告を出した。国全体として、この問題に正面から取り組む必要がある。そんな流れの中で、一石を投じたつもりだ。
一方で、主に子どもと同居する側の立場を代弁する複数の弁護士から「共同親権賛成に偏り一方的だ」という批判もあった。
DV(家庭内暴力)問題を中心に実績のある弁護士は「裁判所で親権者や子どもの面会が否定される背景には、DVや児童虐待が存在しているケースも多い。DV、児童虐待は立証が難しく、安易に共同親権が適用されることにならないか懸念がある」と指摘。「共同親権制度でないから、親権や面会が認められないと訴えるのは、理論のすり替えに他ならない」と主張する。
前回の特集では、メイン見出しに「子ども第一の目線で臨め」(上)「心のケア体制整備急げ」(下)とあるように、視点はあくまで子どもが最優先だという点にあることを、まずは確認しておきたいと思う。
どちらか一方の側に立つのではなく、子どもの利益を優先すべきなのは言うまでもない。この国の現状が、最優先されるべき子どもの利益がないがしろにされているのではないか、という世界からの非難にさらされていることを忘れてはなるまい。
離婚後のスムーズな面会交流が実現しない理由の一つは、激しい感情的な対立が続いているケースだ。
調停に限界があれば、子どもへの影響を緩和する第三者機関などの対処手段が必要だろう。夫婦間の激しい対立やDVに共通するのは、当事者だけで解決するのが難しい、ということだ。家庭裁判所がその機能を十分に果たし切れているとは言いがたい。
すでに社会人になっている遼さん(32)は子どものころ、父親の勤務先の会社の経営が傾いたことをきっかけに父親が母親に暴力を振るうようになり、それがトラウマ(心的外傷)になった。
「あのころはどうしたらいいか分からず、パニックになった」
引きこもり生活が続き、福祉系の大学を卒業して介護職に就いたものの、仕事上のトラブルで心の病に。利用者として通い始めた就労支援会社の女性経営者の励ましと、自らと同じような境遇の主人公を描いた映画「ママかパパか」を見たことが救いになったという。
利用者から正社員である「職業指導員」に採用され、あるとき「昼食作りを手伝って」と、幼いころに親の離婚を経験した十七歳の利用者の少年に包丁を渡すと、少年は手際良く野菜を切ってみせた。「会いたい」と慕う父親は腕利きの板前だった、と聞かされた。遼さんの父親への思いと重なり「嫌いだった自分を肯定できるようになった」。
最近、母親に内緒で父親に「どうしてる」と手紙を書いた。返事はまだ届かないが「僕にとって、たった一人の父親。今も会いたい」と思いを語る。
十組の離婚には十のパターンがあり、一律に判断できる物差しはない。だが、子どもの「会いたい」と願う思いに寄り添う必要がある。現状では、裁判所が公平に仲裁したり、事実の真偽を判断したりできないまま、結論を下すケースが少なくない。時代に合っていないのではないか。
◆科学的知見も必要
立命館大の二宮周平教授(家族法)は、子どもが別居親からも見守られていると確信できるとして「面会交流」の意義を認めた上で、こう指摘する。
「DVが原因で離婚した場合、加害者には治療を含む更生プログラム、被害者にはエンパワーメント(励ましによる力づけ)のためのプログラムが必要。そういった仕組みやルールが日本では不十分だ。法曹界にも心理学など科学的知見が求められる」
時代に合った調停・審判のシステムを確立しなければ、夫婦間の対立が激しいケースで子どもの利益を最優先にした解決への糸口は見えてこないだろう。
中日新聞まで記事の感想についてメール送信をお願いします。
genron@chunichi.co.jp
アクセス数
総計:950 今日:1 昨日:2