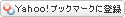令和3年7月24日、東洋経済ONLINE
日本の「子ども連れ去り」に海外が注目する理由 「共同親権」をめぐる日本と海外の大きな溝
レジス・アルノー : 『フランス・ジャポン・エコー』編集長、仏フィガロ東京特派員
7月10日、フランス人のヴィンセント・フィショ氏がオリンピックスタジアムの近く、千駄ケ谷駅前でハンガーストライキを始めた。オリンピック期間中に自らが直面している問題に世界の注目を集めるためだ。2018年8月10日に妻が2人の子どもを連れて去ってから、フィショ氏は子どもたちに会えていない。
目下、離婚裁判が進んでいるが、フィショ氏と妻はまだ婚姻状態にあるため、法律では2人は今も共同親権者だ。もっとも、離婚までの監護権者は裁判所で妻に指定されている。この件で、妻はフィショ氏による家庭内暴力を主張し、フィショ氏は全面的に否定した。村松多香子判事は、ドメスティック・バイオレンス(DV)があったかについては判断しないまま、監護権者として母親を指定した。
マクロン大統領が菅首相に協議を要請
フィショ氏はハンガーストライキの場所と時間を慎重に選んだ。そして、日本の中で世界の注目を集めている場所のそばで、オリンピックの13日前に行動を起こしたのである。
同氏はこれによって、フランスのエマニュエル・マクロン大統領がこの問題に対して何らかの行動を取ることを望んでいる。フィショ氏は2019年に同大統領と在日フランス大使館で会い、この件について問題提起をした。同大統領は同情し、その日の夕食会で当時の安倍晋三首相にこのことを話している。
「だが、それ以来、何の進展もない」と、フィショ氏。フランス大統領府が明らかにしたところによれば、マクロン大統領はオリンピックで来日の際、この問題を協議することを菅義偉首相に求めている。大統領は、数少ない重要な国家元首の1人がはるばるフランスから訪れるのだから、自分の立場は強いと見ているようだ。
マクロン大統領はまた、菅首相が安倍前首相よりも一個人としてこの種の社会問題に柔軟であると信じている。ただし、フィショ氏のもとを訪れることは逆効果だろうと考えているのか、現段階で大統領はフィショ氏を訪れることは予定していない。
フィショ氏の行動は世界の注目を集めている。フランスのAFP、アメリカのワシントン・ポスト、イギリスのフィナンシャル・タイムズなどがこの件を報じている。しかし、マクロン大統領が子の連れ去り問題を来日時に取り上げることを明らかにしたことから、ようやく少し取り上げられるようになったものの、日本のメディアはほとんど沈黙したままだ。
千駄ケ谷駅の改札口には外国人と日本人の何十人もの親(男性の方が多いものの、女性も少なくない)がフィショ氏のもとを日々訪れている。水筒を持ち寄り、同氏を支えている。お互いに自分の物語を語り、泣いている。毎日通っている人もいる。自分の結婚相手と連絡が取れなくなった人もいれば、パートナーとの関係が緊張状態にあり、子どもが連れ去られるのではないか、とおそれている人もいる。
「大阪からバスで会いにきてくれた日本人の父親もいます」とフィショ氏は話す。
「子の連れ去り問題」日本と海外で認識の差
国際結婚をしたカップルの片方が、子どもとともに姿を消して連絡を絶つ、という問題は双方が日本人同士であるより複雑だ。それは、日本と他国の制度や考え方に大きな違いがあるからだ。
例えば日本とフランスの制度を比較した場合、どちらの国も、「子どもの最善の利益」を原則としている。しかし、「何が子どもの最善の利益か」という点において、両者は大きく異なっているように見える。日本の裁判所は、継続性の原則、つまり、子どもの現在の生活状況に特段の問題がなければ、その状況を維持することが子どもの最善の利益にとって重要であると考えている。
他方で、フランスでは両親の相互への愛が冷めたとしても、子どもとそれぞれの親との関係を維持することこそが子どもの最善の利益である、という信念がある。このため、フランスでは両親が離婚しでも双方の親が親権を持つ。
フランスの家族法に詳しいセリーヌ・ケダール=ボーフール弁護士は過去30年間、繊細な事例を扱ってきた。同弁護士によると、「子どもたちは主に同居する親としてどちらかの親を指定されるが、もう一方の親もどうどうと子どもに会うことができる。一般的には隔週の週末とすべての祝祭日の半分だ」と話す。
判事は子どもの「主な住居」としてどちらがふさわしいかを判断する際、いくつかの基準を検討するーー子どもと過ごす時間を持てるかどうか、教育面での世話ができるかどうか、どれくらいの収入があるかなどだ。
「例えば夫が教師で、家で過ごす時間が多い一方、妻が弁護士で極めて多忙という場合は、判事は子どもの家として夫の家を選ぶ」とケダール=ボーフール弁護士は話す。結果的に、フランスでは、両方の親が子どもと十分に過ごすことが認められている。
また、日本の制度と比較した場合大きく違うのは、子どもとの面会を求めることができる人の範囲が驚くほど広いということだ。フランス民法典第371条第4項は次のように説明している。
「家庭裁判所は、子どもの利益のために、親かどうかにかかわらず、特に、その第三者が基本的に安定して子どもおよび親の一方と一緒に住んでおり、子どもの成長、養育費、安定的な生活を提供し、子どもと永続的な感情の結びつきを築いている場合には、子どもと第三者の関係性に関する条件を決定しなければならない」
これが実際に意味することは、祖父母や義理の親、さらには乳母であっても、長い間子どもたちと一緒にいた人なら、両親の離婚後も面会を求めることができるということだ。当然、子どもたちが望んでいる場合だが。
DV被害者を守る制度
共同親権問題を語るときに重要となってくるのが、ドメスティック・バイオレンス(DV)である。カップルのどちらかが伴侶から暴力を受けていて、妻あるいは夫が子どもを連れて去る、というケースも考えられるからだ。この場合、逃げた側が自身と子どもの安全のため身を隠していることもあるだろう。
フランスでもDVは大きな問題だ。フランスでは女性がDVから逃れたいと思ったときの仕組みはこうだ。
「DVの疑いがある場合、裁判所はヒアリングが設定された日から最大6日以内に、被害者に対する緊急保護命令を出すことができる。請求してから数日でヒアリングの日程が決まる。一般的に、例えば女性が木曜日に申請した場合、翌週の火曜日に裁判所でヒアリングが行われ、翌週に決定が下される」(ケダール=ボーフール弁護士)。命令では、加害者を家から退去させることもできる。期間は6月だが、延長も可能である。
これに対し、日本では、DV被害者は逃げるのが基本だ。退去命令を求めることも可能だが、その期間は2カ月であり、その間にDV被害者は自分が住んでいる家から逃げ出さなければならない。このように効果的なDV対策制度がないため、被害者の親は子どもと一緒に逃げて自己防衛しようとするほかない、と子を連れ去る親への偏重を是とする日本の弁護士や非政府組織は説明する。
もっとも、フランスでは、こうしたDVが問題になる場合でも、両親のうち一方が子どもとまったく会えなくなることは通常ない。ケダール=ボーフール弁護士によれば、「子どもを連れ去られた親が暴力的であることが判明した場合でも、心理学者が同席し、判事の監督の下、『面会センター』で子どもと会うことができる。後に、父親が暴力的でなくなったと判事が判断すれば、元夫は段階的に子どもたちと会うことができるようになる」。
一方、日本では両親がそろって同意したとしても、離婚後の共同親権は認められていない。すなわち、両親の別離があった場合、子どもは2つの家庭に属するのではなく、完全な親権を持つ親と一緒に、もう一方の親から離れるべきだという考え方が基本となっている。
「日本では、別離後の面会はイベントであり、日常生活の一部ではなく、面会というイベントは子どもの日常生活を害さない限りで認められる。反対にフランスでは、面会は子どもの日常生活の一部だ」と家族問題を専門とする、ある日本人弁護士は説明する。日本では、残された方の親が判事から面会を認められても、その頻度や時間は申し訳程度のものとなるだけでなく、親権を持つ親によって拒否されれば実現はほとんど不可能だ。
離婚したら子どもの人生から「切り離される」
子どもの連れ去りが容認され、その後は、継続性の原則にしたがって、どちらかだけの親にすべてが与えられる。日本の制度が今後もこうした考えに基づくのであれば、伝統的に主に育児をする側との認識がある妻側だけが主に親権を持つという状況は変わらないだろう。
それどころか、日本人は離婚後に、基本的に親権を持たない親(多くは夫)が子どもの人生から自分が切り離されるという事実や、妻が再婚した場合、夫は完全に子どもの人生から消し去られるという事実を難なく受け入れてきている。
が、一方で若い父親たちはこうした法律を徐々に受け入れないようになってきている。「育児に関して、30代、40代の多くの父親はそれ以前の世代と考え方がまったく違う。育児に関わり続けたいと考えている」と、家族問題を専門とする大畑敦子弁護士は話す。「面会を要求する父親の数はますます増えている」と別の弁護士は付け加える。
実はフランスでも、もともと共同親権が認められていたわけではない。「私が30年前にこの仕事を始めた時には、制度的に母親が親権を持っていた。子どもの近くにいるためだけに妻と一緒にいる、と告白する父親はめずらしくなかった」と、ケダール=ボーフール弁護士は話す。
「2002年に共同親権が法律上の基本原則となった。それ以来、男女間の関係性はまったく違うものになった。もちろん、別れた後のふたりの関係はつねに複雑だ。しかし、双方がお互いに子どもと会い続ける権利を持つことに同意はしている」
今回、フィショ氏の妻と弁護士にも取材を申し込んだが、「繊細な段階」として取材を受けてもらうことはできなかった。
アクセス数
総計:549 今日:1 昨日:0