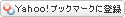平成24年10月29日号、AERA
「連れ去り」容認する司法に現役副市長が実名で告発
離婚や別居を機にわが子に会えなくなってしまう「連れ去り」問題。その蔓延を放置してきた司法のあり方に、現役の副市長が実名で問題提起する。
総務省官僚として公務員制度改革にかかわり、現在は栃木県那須塩原市副市長の渡辺泰之(やすゆき)氏(39)は、2年前から5歳になる一人娘と一度も会えていない。2010年春、妻が突然、実家に長女を「連れ去」ったためだ。教育方針などをめぐり、妻とは意見がすれ違っていたという。
一昨年10月には、妻側が千葉家裁松戸支部に子どもの身の回りの世話などをする「監護者」の資格を求めて審判の申し立てをしたため、渡辺氏側も申し立て。今年2月、同支部は監護者を妻と定め、渡辺氏への娘の引き渡しを認めない審判を下し、9月には最高裁で確定した。
現在、渡辺氏は、一審の審判を下した家事審判官の若林辰繁裁判官に対し、裁判官を罷免できる「裁判官弾劾裁判所」へ訴追するべく、国会議員で構成される「裁判官訴追委員会」に審議を求めている。
現役の副市長という立場も明かしたうえで、あえて実名での問題提起に踏み切った理由を、渡辺氏はこう語る。
「自分のような目にあう親子は、これで最後にしたいんです」
昨年、民法766条が改正され、離婚時は子どもとの面会交流や養育費などについて、「子の利益を最も優先して」取り決めることが明文化された。国会審議でも、当時の江田五月法相が「裁判所は親子の面会交流ができるように努めることがこの法律の意図するところ」と答弁している。
弁護士資格を持つ早稲田大学の棚村政行教授(家族法)は、民法766条改正の趣旨を徹底するためには、司法へのアプローチ以外にも、離婚時に面会交流の必要性をレクチャーする機会を行政が設けたり、面会交流のための場をこれまで以上に増やしたりするなどの制度づくりが不可欠と説く。
また、「離婚後も両方の親が共同養育責任をもつ」というように民法で規定する必要もあるという。
※AERA 2012年10月29日号