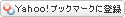平成30年7月6日、東洋経済ONLINE
39歳「離婚」の親権争いに敗れた男が見た真実
単純計算すると3組に1組の夫婦が離婚している日本。そこにいたるまでの理由は多種多様だ。そもそも1組の男女が、どこでどうすれ違い、離婚という選択肢を選んだのか。それを選択した一人ひとりの人生をピックアップする本連載の第2回。現代社会が抱える家族観や結婚観の揺らぎを追う。
■「お父さんに挨拶してほしい」がすべての始まり
「離婚してから、8年間、子どもに会わせてもらえなかったんです。本当に会えたのはつい最近なんですよ」
大地さんは、関東地方の某ファミレスで、おもむろにそう切り出した。
鈴木大地さん(39歳、仮名)は、8年前に2歳下の妻と離婚。短髪の黒髪でがっちり体形だが、元保育士という職業柄なのか、つねに穏やかでおっとりした話し方で、優しいオーラを醸し出している男性だ。誰からも好かれそうな好感が持てる雰囲気がある。
なぜ、大地さんが、妻である里美さん(当時24歳、仮名)と離婚することになったのか、その壮絶な軌跡を追った。
小さい頃から、子どもが大好きだった大地さんは、大学を卒業後、公営施設の保育士という職に就いた。当時、男性保育士は、まだまだ珍しいという時代。働き始めて、2年後に友人の紹介で出会ったのが、同業者の里美さんだった。
里美さんは、かわいかったが、とにかく押しが強い女性だった。勢いに押されて付き合い、1年が経ったころ、里美さんから「お父さんに挨拶してほしい」と切り出された。いつの間にか、あれよあれという間に、結婚まで話が進んでいた。
「結婚まで何回か、ちょっと急ぎすぎじゃないかと感じたんですけど、指輪がどうとか、式がどうとか、その流れを自分で止められないんですよ。妻は別れるか、結婚するかと、2択を突きつけてくれるんですよね。自分から主体的に結婚したいというよりは、向こうに乗っかっちゃったという感じですね。『勢いで結婚』ってこういうことなのかと思ってました」
大々的に結婚式を行った後、あまり間を置かずに、第1子の息子が生まれた。その1年間は、いちばん幸せな時間だったと大地さんは振り返る。当時は、イクメンという言葉が世の中に出始めた走りでもあった。保育士という職業は、ある意味、子育てのプロである。大地さんは、平日でも帰宅すると息子を寝かしつけ、休日も家事に育児にと奔走した。
大地さんは、まさに世間がイメージする、イクメン像そのものであった。フルタイムの共働きということもあり、家事も育児も完全に妻と分担して行い、そこには男女の差などないと思っていた。大地さんは公務員で、経済的にも安定しており、特に不満もなく幸せの絶頂だった。今の時代、はたから見たら、誰もが羨む勝ち組夫婦に見えただろう。
そんな夫婦生活に綻びが見え始めたのは、里美さんが、「仕事を辞めたい」と言い出したことだった。里美さんは、第1子を抱えながらも、数カ月後には職場復帰を果たしていたが、子育てと仕事の両立に悩んでいた。息子のために、少しでも早く帰宅しようとする里美さんを職場の上司は、事あるごとに責め立てた。いわゆる、パワハラだ。
精神的に病んでしまった里美さんは、大地さんとも話し合い、職場を退職することにした。くじけずに、また新しい職場で働けばいい、そう思っていた。しかし、一度職を辞めてしまうと里美さんは、なかなか職を探そうとはしなかった。
日中は子どもと一緒にいてダラダラとしているだけで、時間を持て余してボーッとしている。さらに、ネットゲームに夢中になり、何時間もパソコンの前に陣取っていた。
■マルチ商法にハマり、食事は何種類ものサプリ
そのうち、まるで空虚な心のすき間を埋めるかのように、健康食品のマルチ商法にのめり込むようになった。気がつくと、家中、高額なサプリやフライパンなどの調理器具で埋め尽くされていた。
「退職してから、妻の交友関係がガラリと変わったんです。健康食品のボス格の人の怪しげなセミナーとか、『女の幸せは家族の健康のために生きることなのよ』というセミナーに、すごく楽しそうに出るようになったんです。これはヤバイと思って、それはおかしいよと説得しようとしたんです。
でも元妻も理論武装して、『これは、普通の空気清浄機とは違って、良いものが発生して子どものためにもいいんだよ』と言って、絶対に聞かない。いくら言ってもまるで洗脳されているようで、まったく聞き入れてくれないんです」
いつの間にか、家庭の食事は、何種類もののサプリに変化していた。息子が生まれた直後は、毎日離乳食を作っていたが、そのうち息子の食事も毎食数粒のサプリと特製ドリンクで代用させるようになった。
「2歳とか、3歳の子どものご飯が、皿に何粒かのサプリですよ。さすがにマズイと思って、『こういうものを子どもに食べさせてるのは、俺はいいと思わないよ』と言ったんです。だけど、彼女の理論は、これでビタミンとかミネラルとか、人間に必要なすべての栄養がまかなえるんだから、これほどいいものはないと力説するんです。やはりそれだけではお腹が空いたのか、子どもたちはお菓子を食べていましたね」
こんなものは、毎日は食べられない――、何度も夫婦で話し合ったが、体に良い、と一点張り。それどころか、サプリを食べようとしない大地さんに怒り狂った里美さんは、突然目の前の皿をつかんでたたきつけたこともある。
「なんでわかってくれないの!」
大地さんは、かろうじて皿が当たるのを避けることができたが、頭にでも当たっていれば大ケガになるところだった。
入所時は手取り約20万円だった大地さんの給料は、公務員でしかも管理職まで順調に上り詰めたということもあり、数年後には約35万円まで昇給していた。しかし、その財布を握っているのは、里美さんだった。大地さんには、月3万円の小遣いが渡されるだけで、ほかの支出にはいっさい手をつけることができなかった。
新築で購入した分譲マンションのローン返済は8万円。しかし、それ以外の収入のほとんどが、高額なマルチ商法の商品に費やされていった。夏と冬のボーナスも、空気清浄機や鍋セットなどの高額商品に、おカネが湯水のように消えていく。大地さんは何度もそのおカネの使い道に異議を唱えた。
「値段を聞くと、10万円のフライパンとか当たり前のように買ってるんです。ありえないってなるじゃないですか。『なんでこんな高いもの買ってきてんの?』と言い合いになるんです。でも妻も強い思いをぶつけてくるので、どっちかが折れるしかないんですよ。
おかしいと言えば『責めてる』となじられるし、でも言わなきゃ自分の好きなようにおカネを使われて、それこそ貯金もなくなる。ただ、自分から積極的に別れたかったわけじゃないので、向こうの機嫌を損ねたくなかったんですよ。でも、改善はしてほしいから、なんて言っていいのかわからなかったんです。本当に、どうしようもなかった」
そう言って、大地さんはうなだれた。何とか夫婦の関係を修復させようとしている矢先に第2子の妊娠がわかった。
■第2子出産に立ち会わなかったことを根に持つ妻
第2子の出産には、大地さんももちろん立ち会う予定だった。しかし、運の悪いことに大地さんは胃腸風邪にかかってしまい、医師に、立ち会いは断られた。そのため、泣く泣く出産に立ち会うことができなかった。
「勤務先の保育園でうつされたのか、下痢と嘔吐がひどかったんです。妻にも、本当に悪いと思ったんですが、行けなかったことを、すごく根に持っていましたね。『私が大変なときに、どうしてあなたは病気になったの! ほかのパパは、毎日仕事帰りに寄ってくれたのに、私だけ誰も来なかったからすごく寂しい思いをしたんだから!』と怒り狂ってました。よりによって、なんでこんなタイミングで病気になったのか、確かに僕自身も反省するところもありましたけど、しょうがないですよね」
里美さんは一種の被害妄想のごとく、当時のことを蒸し返しては、大地さんをことあるごとに責め立てた。待望の第2子は、男の子だったが、生まれてから、溝が埋まるどころか、2人の間は、ますます冷めきっていくばかりだった。その頃からすでにセックスレスとなっていた。
第2子出産を境に、里美さんのマルチ商法の波がいったん収まると、まるで埋め合わせるかのように、今度は狂ったような夜遊びが始まった。
大地さんが仕事から帰ってくると、里美さんが入れ代わりに出ていって朝方まで帰ってこない、そんな日が週5日くらい続く。そのうち、土日も大地さんに子どもを預けて、日中は独身の友達と遊びに行くようになる。
当時、里美さんは20代後半、地元の同級生たちは独身生活を謳歌していた。そんな生活が無性に羨ましく感じていたのかもしれない。
「それこそ、学生みたいに夜中に海に遊びに行ったりしてましたね。あとは、飲み会や、クラブとかに行っていたみたいです。百歩譲って、子育ての息抜きにもそういう時間は必要かもしれないと僕は思ったんです。
ただ、子どもが夜起きると、『ママがいないよぉ』と泣きだすんですよ。いい加減にしてほしいって思いましたね。俺は保育士だから子どもの面倒は見られるけど、この子たちは、起きたときにママがいない、寂しいって泣いてるから、せめて夜は出ていかないでくれと、何度も話したんです。だけど、それをいくら言っても構わず出ていってしまうんです」
里美さんの夜遊びはとどまることを知らなかった。まるでそれは遅れて咲いた青春の徒花ようだった。「私は、昼間、子どもの面倒を見てるんだから、あなたは夜見ればいいじゃない――」。そう言い放って、子どもが泣いていても、構わず家を飛び出していった。もうそれを止めることはできなかった。
ある夜、大地さんは、見知らぬ男の車に乗っている里美さんを偶然に家の近くで発見した。里美さんは、大地さんに見せたこともないような笑顔を振りまき、男の車に乗り込んでいった。あっという間に、車は都会の喧騒の中に消え去っていく。まさか、と思ったが、どうしても信じたくなかった。
ある日、日課の掃除をしていると1枚のプリクラが落ちているのが目に入った。男とピースサインをしている無邪気な顔の妻がそこには写っていた。その頃から、妻の浮気は疑惑から確信へと変わっていった。
休日はよく、親戚の法事で出かけると言って出ていった。数日後、義母から電話がかかってきて、「この前は法事で大変でしたね」と言うと、「ええ? 法事なんか、ここ数年1度もないわよ」と驚かれた。
「これまでの話は、全部うそだったのか、と思ったんです。今思うと、その頃にはすでに男ができていたんだと思います」
■シングルマザー支援団体との出会い
里美さんは、二人姉妹の長女として育った。親は厳格で、特に母親には厳しく門限も決められていた。女たるもの、家事も育児も完璧にこなしてこそ一人前、そういう教えをたたきこまれた。里美さんは、そんな家庭環境で育ったため、結婚は、異様に厳格な母親から逃れるための唯一の逃避だったのかもしれない。
実家暮らしだった里美さんは、母親から逃れるためには、結婚して、家を出るしかなかった。
「私は、あんな母親にはなりたくない!」
それが里美さんの口癖だった。自由に生きたいし、自由に子どもたちを育てたい――。里美さんが長年背負っていたのは、重い母の幻影であった。
その幻影を、里美さんは大地さんにふと、見たのかもしれない、あるいは、結婚制度そのものに見たのかもしれない。母から逃れるための結婚が、皮肉にも今度は、里美さんをがんじがらめに追い詰めていた。
「子どものために、そばにいてほしい」という大地さんの言葉は、まさに里美さんの自由を奪う憎むべきものだった。そうまるで、あのときの母のように、また私を縛ろうとしている――。
里美さんは、いつしか、ことあるごとにうつろな目で「離婚したい、別れたい」という言葉を口にするようになった。もちろん、浮気相手の男性がいたということもあった。しかし、それは一過性のものだった。決定的だったのは離婚を後押しする支援者がいたことだ。
その頃から、里美さんは、過激な思想を持つシングルマザーの支援団体の活動にのめり込むようになっていったのではないかと、大地さんは考えている。それは、かつて里美さんがマルチ商法にハマったときとそっくりの熱を帯びていたからだ。
「彼女にとってマルチ商法に代わるものが、シングルマザーの支援団体だったんですよ。我慢して結婚生活を続けるよりも、一人で自分らしく生きたほうがいいという思想のおばさんたちにつかまっちゃったんです。『子どものためにも、離婚しないでほしい』とお願いすると、『私を束縛するのか』『自由を奪う憎いやつ』と言って、僕を敵視して、にらみつけるようになったんです。
僕は、『自分がやりたいことがあればやればいいよ、それは応援する。でも、もし俺のことが嫌いじゃなかったら別れなくてもやれるはず』と、彼女を何度も説得したんです。でも、『ここにいて私は幸せじゃない。自分が幸せなら、子どもたちも幸せになれるから、だから別れなきゃいけない』と、まるで洗脳されたかのように同じことを繰り返すだけなんですよ」
結婚は、自分を縛るもの――、それから解き放たれないと自由になれない。そんな里美さんの強い思いは、いくら大地さんが説得してもまったく揺るぎようがなかった。
お互いの両親を挟んでの話し合いの機会が幾度となく繰り返された。しかし、両親を交えての話し合いは、皮肉にも逆に泥沼と化して、火に油を注ぐこととなる。
「妻の言い分としては、『子育てのはけ口として遊んでいただけで、浮気なんかしてない』という主張の一点張りでした。実の娘がそう言うので、親心としては信じたかったんでしょうね。
義理の両親はむしろ俺の親に対して、『お宅の息子さんは、うちの娘を大切にしてない』と責めるんです。そうすると、うちの親もいい気はしない。結果的に、親同士も険悪な雰囲気になって、離婚ムードが加速していったんです」
■モラハラ夫の烙印
この段階で、ようやく大地さんの中で、離婚という二文字が現実味を帯びてきた。親同士も激しくののしり合っているし、離婚はもはや避けようがない。
しかし、せめて、1歳と3歳の子どもたちは絶対に自分が引き取って育てたい――。そう思うようになった。
親権には、「監護継続性」、つまり、現在子どもと同居している親の現状を尊重するという原則がある。
里美さんはそれを察知してか、離婚調停が始まる矢先に、何の予兆もなく、実家に子ども2人を連れ去った。明らかにシングルマザーの支援団体の入れ知恵によるものだと、大地さんは直感した。
大地さんが親権を取るには、何とかして妻の不貞やこれまでの子どもへのかかわり方を証明する必要がある。その頃から、何か証拠になるものはないだろうかと大地さんは、身の回りを気にし始めた。お互いの予定を書き込んだカレンダーは、妻が毎日遊び歩いていた証拠になるはずだった。
さらに、床に無造作に置かれた里美さんの携帯電話――。そこには、不倫相手とのメールのやり取りがつぶさに残っているはずだった。しかし、里美さんは、大地さんより何枚も上手だった。
「これは、調停で争いになるなと思ったときには、カレンダーが突然家から消えていたんです。彼女の携帯電話も、中身は全部データが消去されていた。僕が気づいたときには、彼女の不倫の証拠になりそうなものは、すべてなくなっていた。男とのプリクラは、日付がなかったので、証拠としてはまったく扱ってもらえなかったんです。
メールのやり取りも、深夜に何度も『子どもが泣いてるから帰ってこい』というメールが僕の携帯には入ってるのに、それは僕の携帯だから、証拠にはならなかったんです。やられた感は、半端なかったですよ」
それどころか、子どもたちを実家に連れ去られた後に、何度も里美さんに電話をかけたことを逆手に取られ、大地さんはモラハラ夫の烙印を押されてしまった。
担当の調停委員は、60代と思しき、頭が固そうな男女だった。子どもたちの親権を取るつもりだった大地さんだが、調停委員は旧態依然とした考え方で、男性の子育てに関してはまったく理解がなかった。
「調停委員は最初から『え? あなたに子どもが育てられるの?』という態度なんです。幼少期は母が育てるものだと当たり前のように言われましたね。60歳くらいのじいさんがそう頭ごなしに言ってくるんですよ。そりゃあ、あなたの時代は、男が外で働いて母が家庭と子育てという家族モデルかもしれませんが、僕らは核家族で共働きで、僕は保育士だし、バリバリ子育てしている。でも、いくら訴えても、まったく通じないんです。法律界はそんな古い社会常識が規範になっているので、本当に、悔しい思いをしましたね」
もし子どもたちの親権を取れたら、昼間大地さんが仕事している日中は、両親が全面的にバックアップして、面倒を見ると両親は快諾してくれていた。しかし、調停員たちは、大地さんが「男」というだけで、全然納得しなかった。
「調停委員に、『日中も自分で子どもの面倒は見るべきでしょ』と言われるんです。昼は、仕事をしているからどう考えても無理ですよね。収入はむしろ、僕のほうが多いんですが、妻は経済的には、義父の援助があり、日中も育てられるというとその主張がそのまま通ってしまった。それまで彼女は、結婚期間は子育てをあまりしなかったと言っても、改心したと言ってますよ、となる。結局、彼らにとって母親が親権を取るのは、出来レースなんですよ」
結局、調停でも妻の言い分が認められ、裁判官は、事務的に親権は母親だと告げた。なぜ、男親というだけで認められないのか――。逆差別ではないのか。あまりに理不尽で非情な裁判所の判断に、大地さんは大きなショックを受けて、崩れ落ちた。親権を争って、さらに裁判まで持ち込むこともできたが、もはや精神的にも肉体的にも、限界が近づいていた。これ以上はもはや争えない――、そう絶望して結果を受け入れるしかなかった。
■子どもとは8年間会えず
離婚してからも大地さんの苦難は続いた。
調停では、子どもたちとは、定期的な面会交流の約束があったが、結果としてそれが守られることはなかった。大地さんは何度も何度も、せめて子どもに会わせてほしいと里美さんに懇願したが、次第に音信不通になることが多くなり、しまいには、住所も変わってしまい、どこに住んでいるかもわからなくなった。そのため、大地さんは、この約8年間つい最近まで子どもと一度も会えなかった。
それでも、大地さんは毎月養育費を支払い続けてきた。毎月1人当たり3万円で、計6万円。これまで一度も滞ったことはない。そして、片時も子どもたちのことを忘れたことはなかった。
「子どもの成長はFecebookにあげるから、そこで見ればいいんじゃない?」
数年ぶりに、気まぐれで連絡があった里美さんから一方的にそう告げられると、大地さんは、毎日、スマホの画面越しに子どもの成長を食い入るように見つめる日々が続いた。里美さんのFecebookページには、子どもたちのことだけでなく、里美さんのプライベートな男性関係が書かれていることもあった。里美さんは、大地さんと離婚後、別の男と結婚と離婚を繰り返していた。もしかしたら経済的にも困っているかもしれない、逆にここがチャンスだと思った。
「お願いだから、子どもに会わせてほしい。何かあったら、子どもたちに経済的にも援助してあげられるから!!」
そう懇願すると、里美さんはあっけなく要求に応じた。8年ぶりに飲食店に現れた子どもたちは、離れ離れになったときの乳飲み子ではなく、しっかりとした子どもに成長して、キラキラして、まぶしかった。
上の子は小学6年生で、思春期に入ったばかりでやんちゃさが目立っている。大きくなったなぁ、ちゃんと育ててくれたんだと、大地さんは、素直にそう思うと感極まった。
「子どもたちは僕にすごく自然に接してくれましたね。本当に、普通に家族みたいな感じ。というか、家族だったんです。それを思うと、この8年間は本当になんだったんだろう、不毛な時間を過ごしていたと思わざるをえませんでした」
そう言って、大地さんは、あふれ出る涙をぬぐった。
■離婚調停の9割以上が親権は母親
大地さんは、保育士を辞め、現在は司法書士として、事務所を立ち上げて活動している。
司法書士の資格を取ったのは、自分自身が、法的な知識に耳を傾けてもらえる地位にないと、何を言うにも説得力がないと感じたからだ。離婚に関しても、あまりにも無知で悔しい思いをした。保育士を辞めて3年間、死に物狂いで勉強をして、資格を取った。大地さんは、これまでの経験を通じて、子どもと自由に面会ができなかったというつらい思いが根底にある。
「今となっては、元妻が悪かったとは思わないです。彼女は彼女で自分を守ろうとしたんだと思いますね。だから、恨みとかそういう感情はないんです。ただ、子どもとの面会が自由にできなかったのは、ずっと、トラウマとして僕の心に影を落としているんです。子どもには、一生会えないんじゃないかと思っていた。それを考えると、やっぱり社会もおかしいと思います。
ママが子どもを取り上げられる悲しみは耐えがたいと思うんですが、パパもそれは一緒なんですよ。なのに、公的機関のジャッジは偏っていると思うんです。男女平等にみてくれない。それには、本当に今でも、憤りを感じているんです。ただ、そんな社会は少しでも変えていければと思っています」
離婚問題に詳しい元裁判官の男性によると、「母親の親権がデフォルトで、父親については問題点をあげつらうのが慣例となっている」という。「建前では、子どもの親権は性別ではなく、どちらが適切に養育できるかだが、明確にそこには男女差別がある」と断言する。今もなお、母親が子どもを虐待しているなど、よほどのことが明らかにならないかぎり、父親が親権を取れる望みは少ないのが実態だそうだ。
裁判所の統計によると、離婚調停(またはそれに代わる審判事件)で子ども親権が母親に渡るのがほとんど。父親に親権が渡るのは1割以下だ。
保育士でもあり、イクメン世代の走りである大地さんが離婚で感じた憤りと理不尽は、現代社会の家族のあり方が大きく変化している中で、個別のケースに真摯に対応できていないずさんな離婚調停の結果でもある。これも離婚というドラマの過酷な現実の1つなのだ。
菅野 久美子 :フリーライター
アクセス数
総計:1239 今日:2 昨日:0